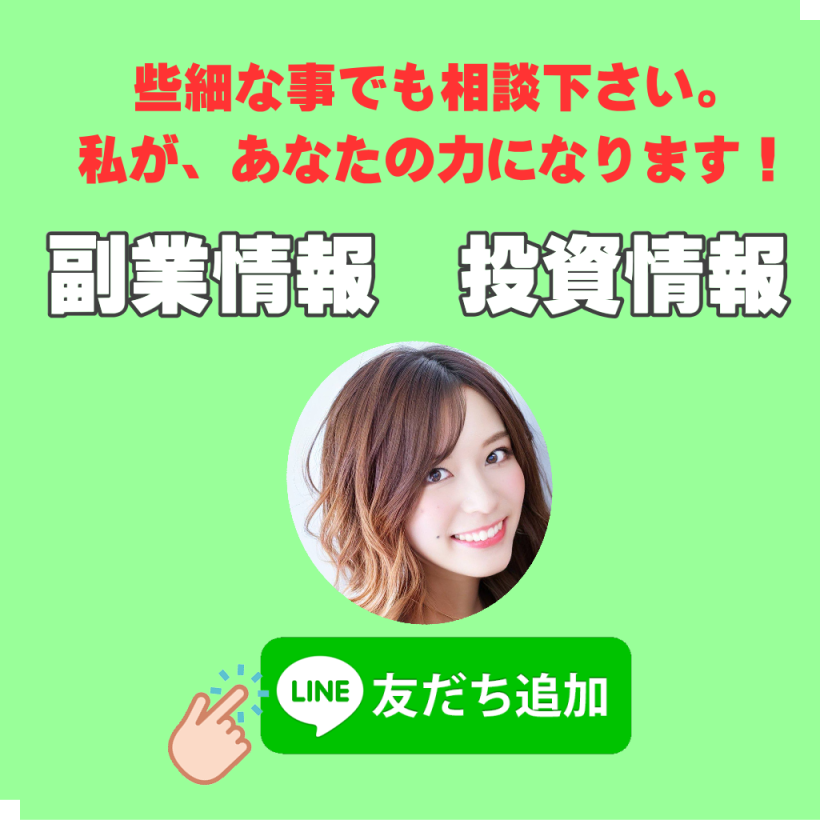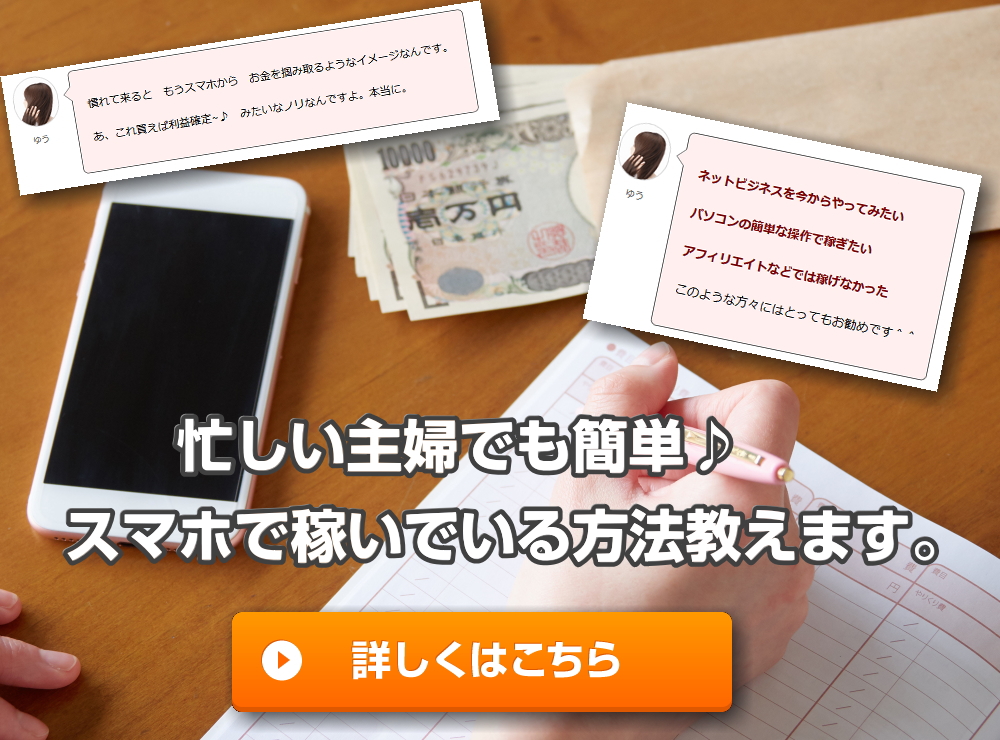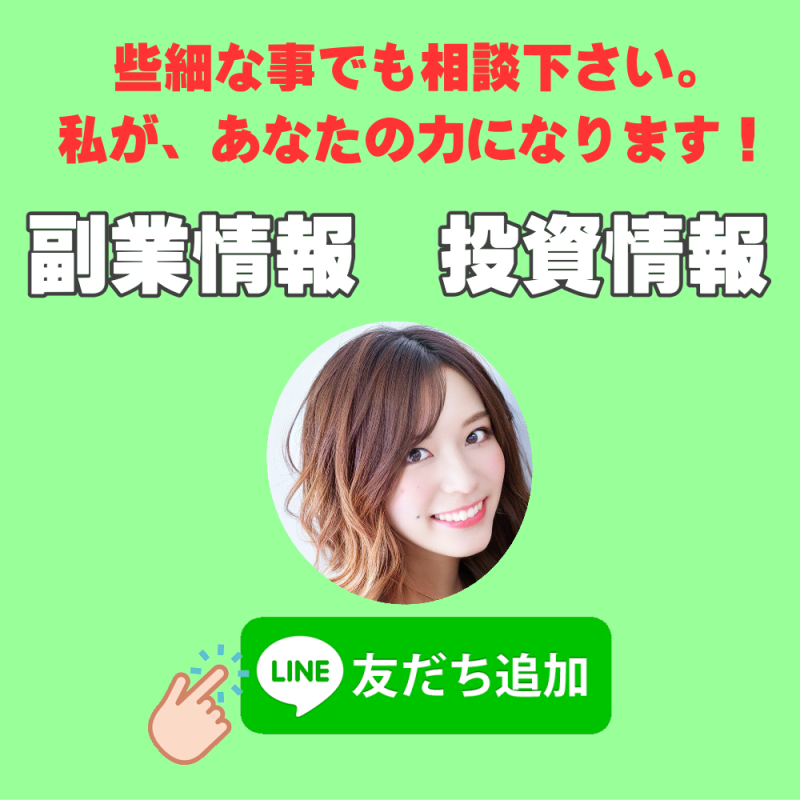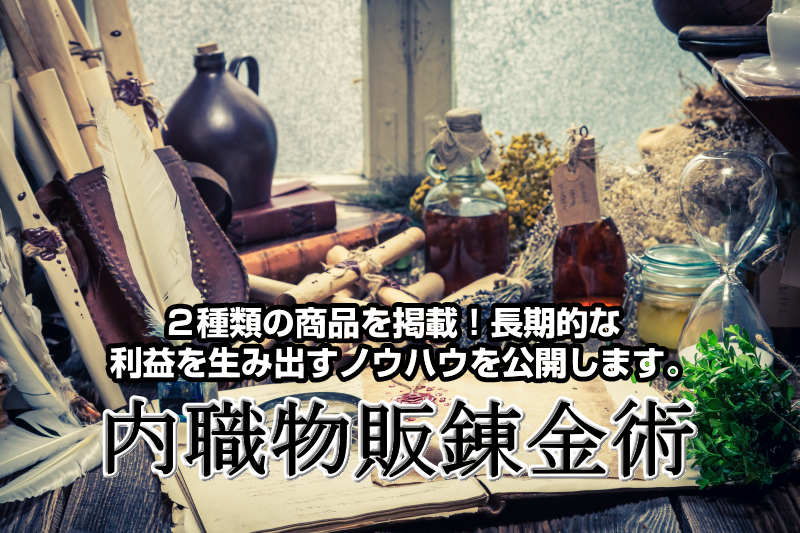ゆうです^ ^
いよいよインボイス制度がスタートしましたね。
せどりや転売をしている事業者で、アマゾンやメルカリなどのアカウントを複数使っている人は少なくないと思います。
この記事では、インボイス制度スタートにあたり
- 他人名義のアカウント
- 家族のアカウント
- 会社と個人のアカウント
など各プラットフォームにおいて、複数アカウントを持っている場合、インボイスはどうなるのかについて書いています。
せどりや転売の収益に関係してくるので、よくわからないまま…ということにならないようにしましょう^^
まずは、インボイスについて再確認していきます。
インボイスとは
 インボイスってものすごく簡単に言うと、厳密な規則に基づいた請求書(適格請求書)のことです。
インボイスってものすごく簡単に言うと、厳密な規則に基づいた請求書(適格請求書)のことです。
税金を納めている人にとって、せどりや転売における仕入れ時の消費税を控除できるかできないかに関わってくるものになります。
ただ、これは事業者間(課税業者)のことであって、商品を個人に販売する場合は関係のないことです。
仕入税額控除をする際、経理における作業において、課税業者からの正確なインボイス(適格請求書)を受け取っておかなければなりません。
もちろん、あなた自身も課税業者であるならば「事業者登録番号」を取得して、インボイスのルールに沿った請求書を発行できるように準備しておくほうが、ビジネスはスムーズにすすんでいきます^ ^

仕入税額控除
 事業者は販売商品を購入した人から預かった消費税を、国に納める責任があります。
事業者は販売商品を購入した人から預かった消費税を、国に納める責任があります。
でも、事業者自身も商品を仕入れる際に消費税を支払っているので、ひとつの商品に対して消費税を二重にかかることになりますよね。
だから、消費税が二重で課税されないようにするために、仕入れの際に支払った消費税を、預かっている消費税から差し引くことが許されています。
この差し引きのことを「仕入税額控除」といいます。
仕入税額控除を行うためには、インボイス制度に則っていなければなりません。
消費税を計算する際に、インボイスの要件を満たしていない場合は、仕入れ分の消費税を差し引くことはできないんです。
注意として、せどりや転売の仕入れを行う時、非課税業者や個人から購入した場合はインボイスを発行してもらえないため、あなたが消費税を全額払うことになります。

アマゾンなどで複数アカウントを作るのはなぜ?
 アマゾンのようなプラットフォームを使用してせどりや輸入転売を行っている場合、特にアマゾンやメルカリなどは有名ですが、1人の名義で複数のアカウントを作ることは許されていません。
アマゾンのようなプラットフォームを使用してせどりや輸入転売を行っている場合、特にアマゾンやメルカリなどは有名ですが、1人の名義で複数のアカウントを作ることは許されていません。
ただ、アマゾンのFBAなどを使用して商品販売や転売を行う際に、万が一アカウントが停止されると大きなリスクになります。
そのリスク回避として、家族の名前などで複数のアカウントを運営し、その全ての収益を自身の所得として申告しているケースが多くあります。
実際には、アマゾンやメルカリの利用規約に違反することになりますが、ビジネスを行う上ではリスク管理として重要なことではあります。

自分自身が悪いことをしていなくても、予期せぬトラブルや競合他社からの嫌がらせなどによって、意図せずアカウントが停止される可能性もゼロではありません。
もしもアカウントが突然停止されてしまえば、それだけでビジネスがストップしてしまいますし、運良くアカウントの停止が解除されたとしても、その間の売上はゼロになってしまうことになるわけです。
となると、事業者にとってはアカウントの停止は重大な問題になってきますよね(⌒-⌒; )
それでも、規約違反を知りながらもリスクを回避するために、家族などのアカウントを複数運用している事業者も多いようです。
ただし、規約違反以外にも、今回のインボイス制度の導入によって税務上のリスクも増えることを理解しておく必要があります。

アカウントの名義が違う場合でも、事業者のインボイス番号が使えるか?
ズバリ、あなたが仕入れや販売で使用しているアカウントが、事業者名とは違う別のアカウント名義である場合、事業者のインボイス番号を使用することはできません。
例えば、ソニーが日立のインボイス番号を使ってしまうと深刻な問題となるのは誰でもわかると思います。
これは、個人間や個人と法人間であっても同じです。
今後は、Amazonやメルカリに限らず、インボイス番号の入力(インボイスの発行事業者であるかどうかの確認)を求める事業者が増えてくるんじゃないでしょうか。
ちなみに、Amazonでは、インボイス番号が入力されない場合、その業者はインボイスの発行ができないことが明確になるようになっています。
これにより、他人名義のアカウントでインボイス発行事業者の登録をすると問題が生じてしまいます。
そのため、自分自身がインボイス発行事業者の登録を行っても、他人名義のアカウントを使用している場合には注意が必要になってきます。
たとえばAmazonをっ使って販売をしている課税業者の場合、出品管理画面のセラーセントラルにログインして、インボイス登録番号を入力する必要があります。
入力時の注意点としてこのような記載があります
・消費税の設定ページの発送元住所のフォーマットが正しいか
・出品用アカウント情報の会社住所のフォーマットが正しいか
・番号取得時に申請した事業者名と入力している事業者名が一致しているか
参考:アマゾンセラーセントラル
アマゾンは出品者に変わって請求書を発行してくれますが、その請求書に記載される出品者名と適格請求書発行事業者登録番号の名義が一しない場合、セラーセントラルに入力した適格請求書発行事業者登録番号は無効となり、請求書への表示等が行われない場合があるようです。
実際、私自身が問い合わせをしたら、Amazonビジネス マーケットプレイス事業部 インボイス制度担当者からの返答は以下でした。
fa-envelope-open-o複数の会社で複数の出品登録を行っている場合、それぞれ対応する会社の適格請求書発行事業者登録番号を入力ください。同一の会社で複数の出品登録を行っている場合、当該会社の適格請求書発行事業者登録番号を入力ください。
また、同一の登録番号を入力するアカウントの正式名称・販売事業者名を一致させてください。
つまりシンプルに言うと、アカウント名とインボイス番号登録事業者の名前が一致していなければならないということですね。

アカウント名義が違う場合の対処法
他人(複数)のアカウントを利用している場合に考えられる選択肢について詳しく説明します。
例えば、個人事業主であるAさんが自身のアカウントと、ご家族であるBさんのアカウントを利用している場合
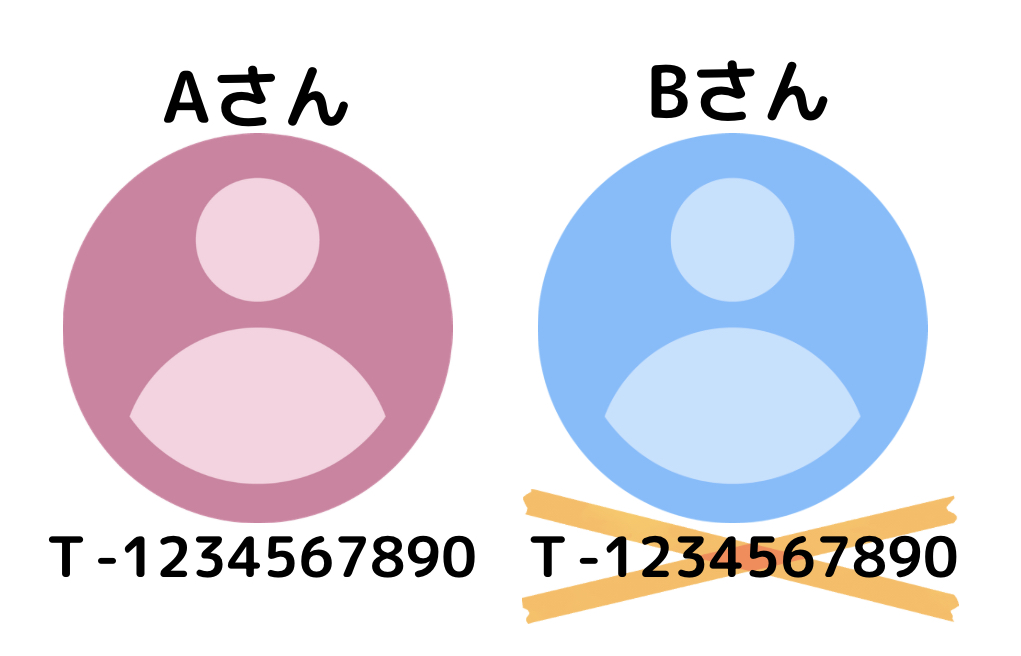
Aさんのアカウントは実際の出品者や登録事業者と一致しているため、Amazonでのインボイスナンバーの登録は可能ですが、Bさんのアカウントはそうはいきません。
つまり、Aさんのアカウントのみインボイスを登録し、Bさんのアカウントは登録しないということになります。
ただ、実際にはこの選択肢は現実的ではないように思います。
というのも、仕入れにおける税額控除がアカウントにより変わってくることになるからです。
ですから、仮にAmazonのシステム上でAさんとBさんが同じインボイス番号の登録ができたとしても、税務上の問題が起こる可能性があります。
個人事業主の方は、通常は自身の名義でアカウントを作成し、取引を行っていることが多いですが
法人で事業を行っている場合は、家族や社員の名義でアカウントを使っていることもあります。
例えば、株式会社○○という法人があり、社長のCさんと役員のDさんがそれぞれ自分の名義でアカウントを使って、株式会社○○の所得として申告している場合、

Cさん、Dさん、2つのアカウントが法人名義ではないため、どちらのアカウントにも法人のインボイスナンバーを登録することはできません。
この場合の選択肢としては
- 新たに法人名義のアカウントを作成し、インボイスナンバーを登録してアカウントを育てていく
- インボイス発行事業者を選択せずに売上に影響を受ける可能性を受け入れる
この2つになります。
せどりや物販などを行っている方にとっては、新たにアカウントを育てることは手間や時間がかかることはわかっていることだと思います。
どちらの選択肢を選んでも、一時的には売上が減少する可能性があります。
もし売上が減少してしまった場合、これまで通りAmazonでの出品を続けるのか、他の販路を開拓するのかなど、ビジネスの展開方法を検討する必要が出てくるかもしれません。
最後に
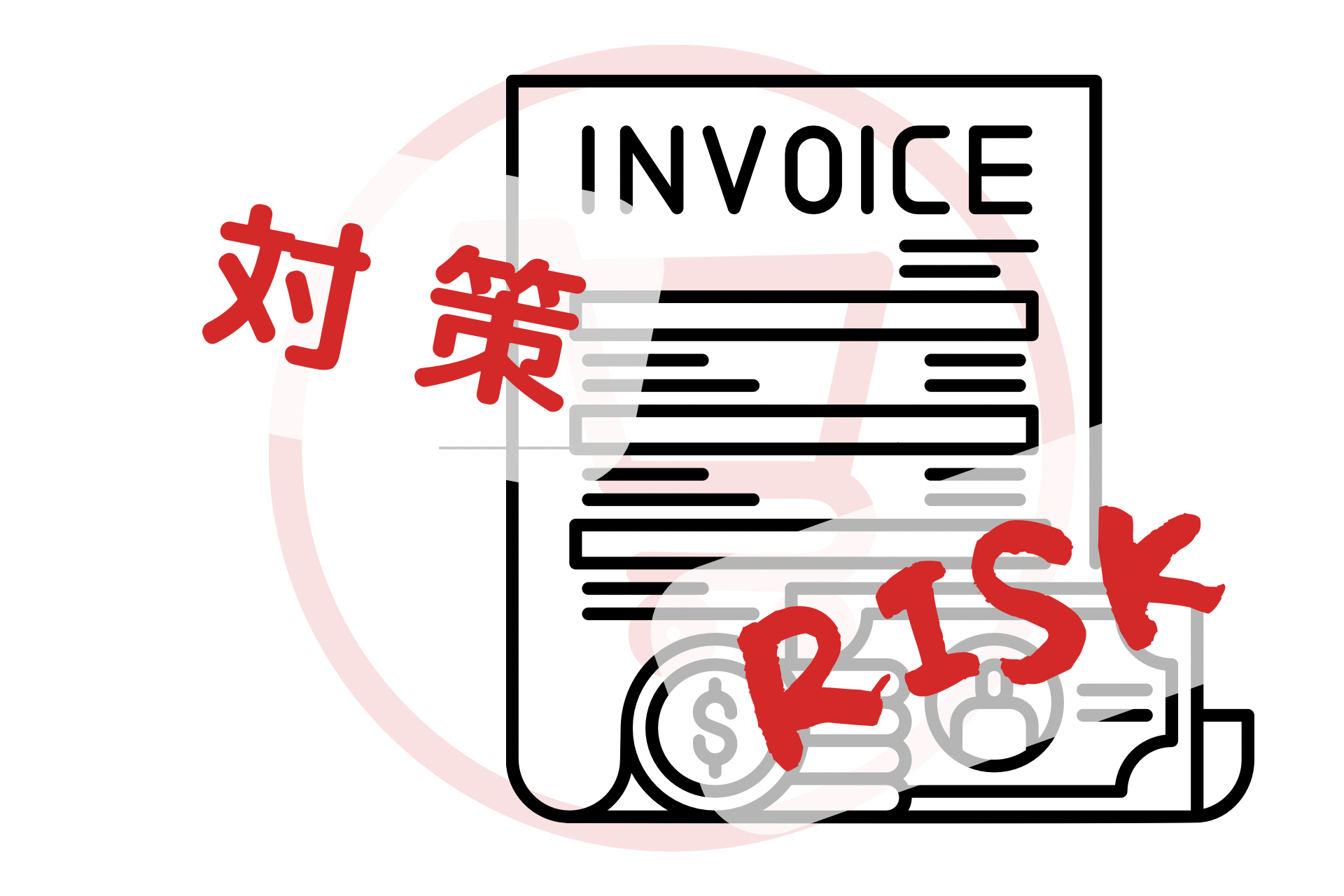 今回はAmazonなどで複数のアカウントを使用している場合のインボイス導入によるリスクについて解説しました。
今回はAmazonなどで複数のアカウントを使用している場合のインボイス導入によるリスクについて解説しました。
インボイス(適格請求書)の導入によって体制の変更を考えざるを得ない可能性もあります。
これからビジネスを始める予定の方であれば、今から注意すれば良いですが、既に他人のアカウントでビジネスを始めている方にとっては懸念すべき事案かもしれません。
まだ悩んでいる方は、アカウントとの関係も考慮しながら将来の展開を考える必要がありますね。











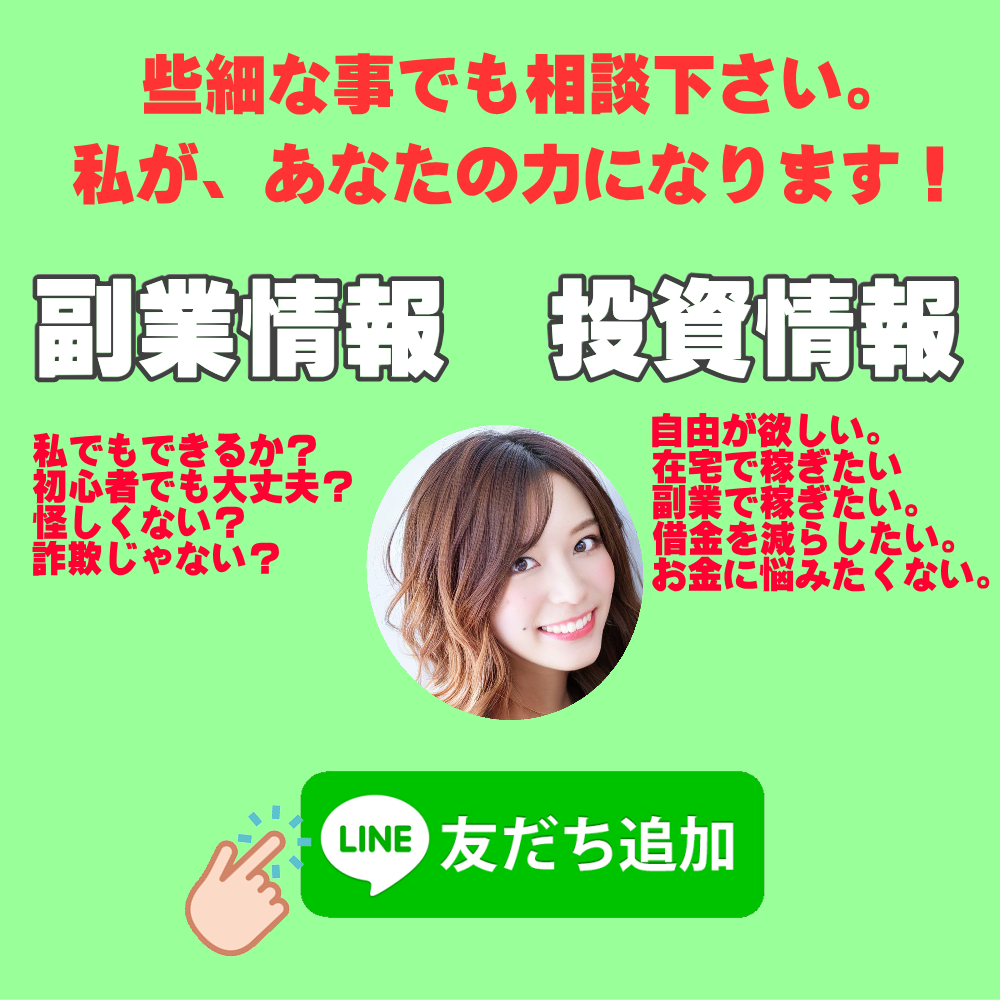
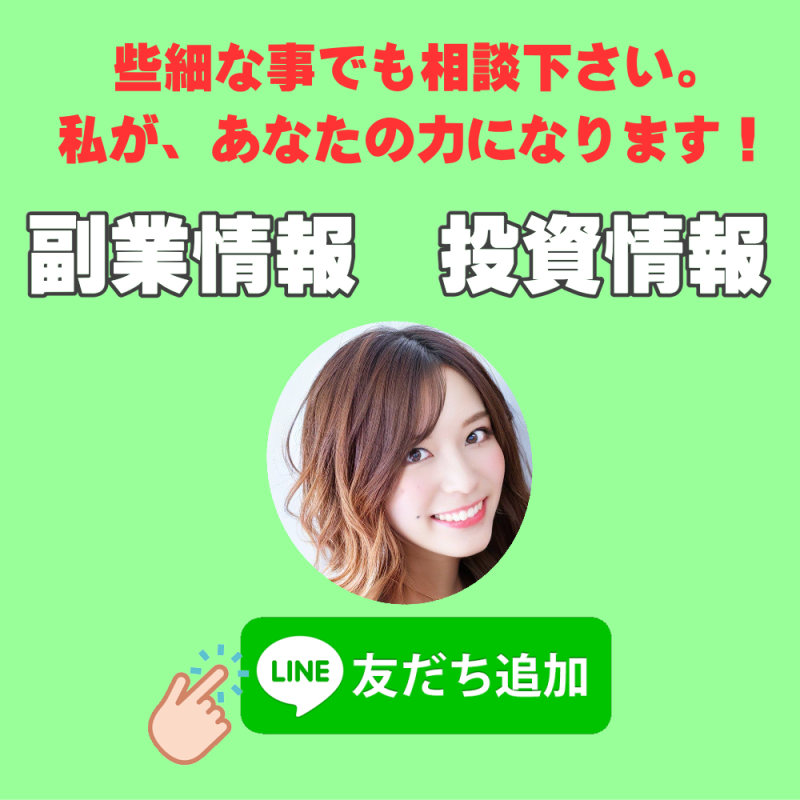









![[TITAN]北野浩のタイタンは悪魔か天使か⁈今どきの AI便利ツール](https://moms-work.net/wp-content/uploads/2023/11/IMG_2500-150x150.webp)